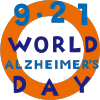認知症をよく理解するための9大法則・1原則
公益社団法人認知症の人と家族の会副代表理事
社会福祉法人財団石心会理事長
川崎幸クリニック院長
杉山 孝博
物忘れがひどくなって同じことを何度も繰り返したり、家族の顔や自分の家が分からなくなるようなことが身内に起こったとき、どの家族も、そのことをどう理解し、どう対応してよいか分からず大混乱に陥ります。奇妙にみえる認知症の症状も、記憶力・理解力・判断力・推理力などの知的機能の低下した人にとっては十分に納得できる言動ではないかと思います。誰にも理解しやすいように、『認知症をよく理解するための9大法則・1原則』をまとめてみました。
1.第1法則 記憶障害に関する法則
記憶障害は認知症の最も基本的な症状で、「記銘力低下」「全体記憶の障害」「記憶の逆行性喪失」という、3つの特徴があります。この特徴を頭に入れておけば、認知症の症状の大部分はすっきり理解できるようになります。
ところで、最初に私たちが心得ておかなければならないことは「記憶になければその人にとって事実ではない」ことです。まわりの者にとっては真実であっても、当人には記憶障害のために真実でないのが、認知症の世界では日常的であることも知っておくことは大切です。
(1)記銘力低下(ひどい物忘れ)の特徴
見たり、聞いたり、行ったりしたこと、つまり体験したことをすぐに思い出す力を記銘力と言いますが、認知症が始まると、まず記銘力が低下します。ひどい物忘れがおこるわけです。
認知症の人は同じことを何回、何十回も繰り返しますが、これはその度に忘れてしまい、初めてのつもりで相手に対して働きかけているのです。丁寧に教えた後、本人が「ああ、わかったよ」と返事をしても安心できません。また同じことを繰り返します。返事した瞬間に教えられたことを忘れてしまうからです。繰り返して教えても、効果がないばかりか、「この人はくどい人だ、うるさい人だ」と受け取られるだけですから、むしろしない方がよいのです。
ところで、物忘れのために同じことを繰り返すのは、認知症の人ばかりでしようか?
外出しようとして玄関まで来たとき、「ガスの元栓を閉めてきたかしら」とか、「アイロンのコンセントを抜いてきたかしら」と心配になれば必ず確認に行くはずです。
このように、気になることを忘れた場合に繰り返すのは人間の本性ですから、認知症の人だけが異常であると考えないことが大切です。
(2)全体記憶の障害の特徴
これは、「出来事の全体をごっそり忘れてしまう」ことを言います。私たちの記憶力ははかないもので、細かいことはほとんど忘れてしましますが、大きな出来事、重要と感じたことは記憶にとどめます。ところが、認知症が始まると自身が体験した出来事全体を忘れるようになります。
訪ねてきた人が帰った直後に、「そんな人は来ていない」と言い、デイサービスから帰った後「今日はどこに行ったの」と尋ねられて「どこも出掛けないで一日中家にいた」と言うことがあります。
周囲の人は、明らかな事実を本人が認めないことに驚いて、正しいことを教え込もうとします。
「隣のおじさんが来て、先ほどまで楽しそうに話していたでしょう」とか、「これはお父さんが作った作品だけど、どこで作ったの」などと、手がかりを与えて思い出させようとしても、うまくいかない場合が多いものです。
逆に、「誰も尋ねてこなかったし、デイサービスにも行った覚えがないのに、この人はどうして私に間違ったことを思い込ませようとしているのか。ペテンにかけようとしているのではないか」と疑念を増し、混乱に拍車をかけることになりかねません。
それよりも、「体験したことを忘れるのが認知症の特徴だから、思い出せないのは仕方がない。でも、デイサービスで楽しく過ごしてしたのだから、思い出せなくてもそれでよいのではないか」と割り切るのがよいでしょう。
食べた直後に「まだ食べていないから、早くご飯を用意して」「食事をさせないで殺すつもりか」という場合に、この法則が適用できます。
認知症の人は、ある時期、異常な食欲を示すことがあります。―人分を食べても空腹感が残っていて、しかも食べたことを忘れる(細かい献立の内容を忘れるだけではない)ため、前述の要求が出てくるわけです。
「今食べたばかりでしょう。これ以上食べるとおなかをこわすからダメよ」という言い方はダメで、「今、準備しているから少し待っていてね」「おなかがすいたのね。オニギリがあるからこれを食べていてね」のように対応した方がうまくいきます。
(3)記憶の逆行性喪失
「記憶の逆行性喪失」とは、蓄積されたこれまでの記憶が、現在から過去にさかのぼって失われていく現象をいいます。
「その人にとっての現在は、最後に残った記憶の時点」になります。
この特徴を知っていると、認知症の人のおかれている世界を把握することができ、どのように対応すればよいかもわかってきます。
配偶者の顔が分らなくなり、嫁を妻と思い込んでトラブルを引き起こすことがあります。昔に戻って、「自分の妻は30歳代の若い女性」と思い込んでいる本人にしてみれば、目の前の老婦人は自分の妻ではありえないし、イメージに一致する嫁が自分の妻であると考えるのは当然といえます。
「何十年も連れ添った私を忘れるなんて!」「お義父さんは嫌なひと!」と家族は嘆き、気持ち悪がりますが、それよりも「奥さんは何をしていらっしゃるの」「ご飯の支度をしなければならないので、また後でね」と言ったほうがうまくいきます。
夕方になるとそわそわして落ち着かなくなり、荷物をまとめて、家族に向かって、「どうもお世話になりました。家に帰らせてもらいます」と言って、丁寧に挨拶して出かけようとすることは認知症の人にしばしば見られます。夕暮れ時に決まって起きますから、“夕暮れ症候群”と呼ばれています。
30~40年前の世界に戻った本人にとって、昔の家と雰囲気の違う現在住んでいる家は他人の家であり、夕方になれば自分の家へ帰らなければという気持ちになるのだと考えれば了解できるのではないでしょうか。
そういう人に向かって、「ここはあなたの家ですよ」と説得しても通じません。玄関に鍵をかけて出さないようにしたりすると、「よその家に閉じ込められた」というとらえ方をして、大暴れするのも無理もないことです。大事なのは、その状態の本人の気持ちを一旦受け入れて、「お茶を入れましたから飲んでいってください」、「夕食をせっかく用意したので食べて行ってください」と勧めると落ち着いてきます。
本人のしっかりしていたかつての状態を知っていて、認知症になったことを認めたくない家族には、本人の状態に合わせて演技をすることが難しいかもしれません。
本人が変なことを言っていると感じたとき、「記憶の逆行性喪失の特徴」を思い起こすことで、混乱が早く治まるのは間違いありません。
2.第2法則 症状の出現強度に関する法則
認知症の症状がより身近なものに対してより強く出るというのがこの法則の内容です。
認知症の人は、よく世話をしてくれる介護者に最もひどい症状を示し、時々会う人や目上の人にはしっかりした言動をするのが特徴です。このことが理解されないため、介護者と周囲の人との間に認知症の理解に深刻なギャップが生じて、介護者が孤立することになります。
医師や看護師、訪問調査員などの前では、普段の状態からは想像できないほど上手に応答するので、認知症はひどくないと判断されてしまいます。介護者は、専門家でさえ本当の認知症状態が理解できないのだと思い、絶望と不信に陥るのです。
認知症の人はなぜこうした「いじわる」ともとれる行動をとるのでしょうか。私は次のように解釈しています。
幼児は、いつも世話をしてくれる母親に対しては甘えたり、わがままを言って困らせますが、父親やよその人に対してはもっとしっかりした態度をとるものです。母親を絶対的に信頼しているから、わがままが出るのです。認知症の人も介護者を最も頼りにしているから認知症の症状を強く出すと考えるのは、類推のしすぎでしょうか。
「自分にとって不利なことは絶対認めない」というものです。
言い返しがあまりにも素早くしかも難しいことわざなどを交えてするので、周囲の者は本人が認知症になっているとはとても思えません。しかし、言い訳の内容には明らかな誤りや矛盾が含まれているため、「都合のよいことばかり言う自分勝手な人」「嘘つきだ」など、本人を低い人格の持ち主と考えて、そのことで介護意欲を低下させてしまう家族も少なくないようです。
こうした認知症の人の言動には、自己保存のメカニズムが本能的に働いているにちがいありません。つまり、人はだれでも、自分の能力低下や生存に必要なものの喪失を認めようとしない傾向をもっており、認知症の人も同様なのです。
「自己有利の法則」を知っていると、無意味なやりとりや、かえって有害な押し問答を繰り返さずに混乱を早めに収拾することができるようになります。
日々の介護で混乱されている家族は、「自分たちはこの法則で説明できる症状に振り回されているのではないか」と考えてみて下さい。
認知症の人は、認知症が始まると常に異常な行動ばかりするわけではありません。正常な部分と認知症として理解すべき部分とが混じり合って存在しているというのが、「まだら症状の法則」です。
本人の言動が認知症の症状であるのか、そうでないのかをどう見分けたらよいでしょうか。介護者の最も大きな混乱の原因の一つは、うまく見分けられなくて振り回されることにあります。初めから認知症の症状なのだとわかっていれば、そして、対応の仕方をうまくすれば、認知症による混乱はほかなりなくなります。
「常識的な人なら行なわないような言動をある人がしていて周囲に混乱が起こっている場合、“認知症問題”が発生してるのだから、その原因になった言動は、“認知症の症状”である」と割り切ることがコツです。
物忘れはあるものの、趣味豊かで日常生活では問題ない人から「私の大事な着物を隠したでしょう。返しなさいよ」と、身に覚えのないことを毎日言われたら、誰もがパニック状態になるに違いありません。しかし、寝たきりで全面的に介助の必要な人が言った場合には、「またおばあちゃんがおかしなことを言っている。どうせ本気で言っているわけではないので、聞き流しておこう」となります。
言動そのものよりも周囲のとらえ方で問題性が大きく変化するのです。
認知症の人は、第1法則の記憶障害に関する法則が示すように、自分が話したり、聞いたり、行動したことはすぐに忘れてしまいます。しかし、感情の世界はしっかりと残っていて、瞬間的に目に入った光が消えたあとでも残像として残るように、その人がその時いだいた感惰は相当時間続きます。このことを、「感情残像の法則」といいます。出来事の事実関係は把握できないのですが、それが感惰の波として残されるのです。
認知症の人の症状に気づき、医師からも認知症と診断されると、家族は認知症を少しでも軽くしたいと思い、いろいろ教えたり、くわしい説明をしたり、注意したり、叱ったりします。しかし、このような努力はほとんどの場合、効を奏しないばかりか、認知症の症状をかえって悪化させてしまうのです。
認知症の人は、記憶などの知的能力の低下によって、―般常織が通用する理性の世界から出てしまって、感情が支配する世界に住んでいると考えたらよいでしょう。
介護に慣れてくれば、多くの家族は、感情を荒立てさせない介護ができるようになりますが、少しでも早く楽な介護をするには、4つのコツがあります。
第1のコツは、「ほめる、感謝する」
どのようなことをされても、「上手ね」「ありがとう。助かったわ」などと言い続けていると、次第に本人の表情や言動が落ち着いてきます。
第2は、「同情」
「ああ、そう」「そういう事があったのですか」「大変ですね」のように相づちをうつことです。
第3のコツは、「共感」
「よかったね」を話の終りに付け加えると「共感」になります。
「ご飯、おいしかった?よかったね」「その着物、よく似合いますよ。良かったね」「雨があがって晴れましたよ。良かったね」とようにします。文字で読むと、話の内容と「よかったね」が、どうして結びつくか分かりませんが、繰り返し話し掛けることで、本人は介護者との間に共感をもつようになり、穏やかな表情になってくるのは間違いありません。
混乱の真っただ中にある介護者は「よかったね」から始めたらどうでしょうか。
第4のコツは「謝る、事実でなくても認める、演技をする、嘘をつく」
認知症の人では「忘れたことは本人にとって事実ではない」「本人の思ったことは本人にとって絶対的な事実である」という原則があります。
食べたことを忘れてしまえば、「食べてない」のが事実。「百万円を貸した」と思い込んでいる人が「借りた金をかえさないのはけしからん。金を返してくれ」と請求するのは当然です。
それを否定して、「ご飯は食べたばかりでしょう」「借りてもいないのに変なことをいわないで」と言うと、こだわりがますます強くなって混乱が続くだけです。
それよりも、「今、夕食の支度をしていますからもう少し待ってくださいね」「今は手元にお金がないので、あす銀行から下ろしてお返しします」と、本人の思い込みをいったん受け入れながら、結論を別の方向にもっていくほうが本人の納得を得やすいのです。
つまり、本人の世界に合わせてセリフを考え、演技する俳優になったつもりで、対応するのがよいのです。
「あるひとつのことに集中すると、そこから抜け出せない。周囲が説明したり説得したり否定したりすればするほど、逆にこだわり続ける」という特徴がその内容です。
ある人とある人との間に何らかのこだわりが生じた場合、普通、相手を説得したり、相手に説明したり、命令したりしてそのこだわりを解消しようとします。ところが、認知症の世界ではこの方法はほとんど通じません。
「こだわりの原因が分かればその原因を取り去るようにする」「そのままにしておいても差し支えなければそのままにしておく」「第三者に入ってもらいこだわりを和らげる」「関心を別のことに向ける」「地域の理解・協力を得る」「一手だけ先手を打つ」「本人の過去を知る」「長期間は続かないと割り切る」、などの方法が認知症の人のこだわりに対応する基本的なやり方です。
具体的な例を見ていきましょう。
まず、「こだわりの原因が分かればその原因を取り去るようにする」のが第1の対応方法です。
初老期の女性が、自分に対して夫が激しい浮気妄想を持つようになったと訴えて受診しました。
話を聞きますと、1年程前から物忘れがひどくなり物を紛失するようになったため、印鑑や預金通帳を奥さんが保管することにして、夫が請求しても渡さないようにしたということでした。
「自分にとって大切なものをあなたがもっていってしまったと考えて、ご主人はあなたに対し猜疑心をもったのです。請求されれば通帳や印鑑を渡しなさい。無くなっても再発行や改印届を出せばよいのだから」
とアドバイスをしました。
翌月の診察日に奥さんがやって来て、「先生の言われた通りにしましたら、浮気妄想はきれいになくなりました。あれは、本当に認知症だったのですか?」
第2番目は「そのままにしておいても差し支えなければそのままにしておく」ことです。
介護者は誰でも、認知症の症状を軽くしようと工夫しながら対応します。介護専門職は、一つ一つの症状を「問題」としてとらえ、問題解決のため努力します。
それぞれは決して間違いではありませんが、効果がえられないことも少なくありません。そのようなとき、努力や工夫が足りないと考えて働きかけを強めると、これまで述べてきたように、認知症の症状がひどくなる場合が多いものです。
「このままにしておいて何が問題か。命に別条なければこのままにしておいてもよいのではないか」と発想を変えるのもひとつの方法です。
第3の対応の仕方は、「第三者に入ってもらいこだわりを和らげる」。
「身近な人に激しい症状を示し、他人にはしっかりした言動をする」という認知症の特徴を応用するのです。
「年金が無断で遣われている」と思い込んでいる本人に対して、当事者である家族が通帳を見せながら、「1円も引かれていないでしょう」と説明しても信じません。
しかし、郵便局員や銀行員が「大丈夫ですよ」と言うと安心します。いわゆる社会的権威者や目上の者などの言うことは受け入れやすいので、そのような人物が登場する場面を作ることで、こだわりが軽くなるものです。
第4番目の対応のコツは「関心を別のことに向ける」。
説得するよりも、別なものに関心を向けることにより強いこだわりを鎮めることができます。
趣味や本人が関心を持つことに対しては、場面転換しやすいものです。
「お母さんの好きな歌を聞かせてください」「洗濯物を畳むのを手伝っていただけませんか。お願いします」というように話を持っていくと、興奮やこだわりが和らぎ、好きな歌を楽しそうに歌い、洗濯物をせっせとたたみ始めることもあります。
趣味や特技のない人に対して、食べ物は最終的な切り札です。本人の好きな食べ物をいつも用意しておいたほうがよい時期があります。
昔の思い出も場面の切り替えに有効です。いなかの生活、会社での仕事、子育て。戦争体験のある人なら戦時中のこと。本人がいつも話していることがあれば、その話題を持ち出すのがよいでしょう。
「こだわり」に対する、第5番目の対応の仕方は、「地域の理解・協力を得る」。
夜間の騒音、ごみ出し、徘徊、隣人への被害妄想など、地域社会とのかかわりをもつ認知症の症状は少なくありません。こんな時、家族は、「遠慮」「気兼ね」「陳謝」など、近所への気遣いという重荷を背負うことになります。
近所への迷惑を考えて、鍵をかけて外出できないようにする、薬を使って興奮を静める、言い聞かせるなどの対応をしてもうまくいかず、混乱を深めることになりかねません。逆に、地域の理解があれば深刻な症状が軽くなります。
「義父が近所の薬局でせっけんを万引きしていることに気付いたとき、目の前が真っ暗になりました。先生のお勧めによって、石鹸を持ってお店の方に事情を話しました。『あんなに元気だった方が認知症になったとは知りませんでした。大変ですね。私たちも注意しますが、せっけんが見つかったら返していただければ結構です』と言っていただいてほっとしました」
これは私が訪問診療をしていた介護者の体験です。「明日はわが身」「お互いさま」という理解が地域に根付いていれば、「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」が可能になると確信しています。
第6番目の対応の仕方は、「一手だけ先手を打つ」という方法です。
症状を抑えることができなくても、症状からくる介護負担を軽くするため「先手をうつ」というやり方です。
郵便物をしまいこむ症状がある場合、大事な郵便物を紛失されると大変です。対応法としては、郵便が届く時間を計って大事な郵便物を取り出す(不要なものは残しておいて)、郵便受けを別に設置するなどの対策をとるのがよいでしょう。
「先手をうつ」という方法は、症状を直接治すのではないので、歯がゆく感じるかもしれません。いずれにしても「症状はいつまでも続かない」ので、最も現実的な方法のひとつと言えるでしょう。
「こだわり」に対する第7番目の対応法は、「本人の過去を知り、こだわりの思いを理解する」ことです。
認知症の人の強いこだわりには、かつての体験が背景にある場合が多いようです。
ある特別養護老人ホームに施設内徘徊が止まらない二人の認知症の女性がいました。疲労を考えて職員が努力しましたが、徘徊が止まらなかったということでした。
家族に本人たちの過去の体験を尋ねましたところ、一人は昔ハイキングに行って子供を山中で見失って必死に探しまわった経験があり、もう一人は、終戦時満州にいてかろうじて最後の引き揚げ列車に乗って内地に帰った体験を持っていました。つまり二人の女性の脳裏には、「子供を失ってしまう」「外地に取り残されてしまう」という思いが染み付いていて、歩き続けないと気持ちがおさまらないという状況をひき起こしているものと考えられました。
第8の対応法は、「長期間は続かないと割り切る」というものです。
金銭や物に対する執着のように「生存に直結する症状」は何年も続くことがありますが、一般的に、一つの症状は長く続かないで半年から1年ほどで別の症状に変わっていくという特徴があります。
介護職や家族の中には、積極的な働きかけをしなければ症状が軽くならないと思っている人がすくなくありません。そのような人たちに「1~2年前に困っていた症状は何ですか」と尋ねると、多くは現在困っている症状とは違った症状を答えます。
それを確認した上で、「1~2年前に困っていた症状は今消えているでしょう。同じように、現在の症状も半年から1年ほどで消えると思います。何年も続くものと決めつけないで、気楽に考えませんか」と話しますと、安心した表情になるものです。
7.第7法則 作用・反作用の法則
認知症の人に対して強く対応すると、強い反応が返ってきます。認知症の人と介護者の間に鏡を置いて鏡に映った介護者の気持ちや状態が、認知症の人の状態です。
「第6法則 こだわりの法則」で取り上げましたが、「そのままにしておいても差し支えなければそのままにしておく」ことです。
「押してダメなら引いてみな!」というように対応するのが良いでしょう。
老年期の知的機能低下の特性や、第1~第7法則でまとめたような認知症の特徴を考えれば、認知症の症状のほとんどは、認知症の人の立場に立ってみれば十分理解できるものである、という内容の法則です。
認知症の人の言動を正しく了解する上では、過去の経験が現在の認知症の症状と深い関連をもっている場合も少なくない事を覚えておいて下さい。周囲の人は、本人の生活歴・職業歴を詳しく知って、認知症の人の気持ちを理解するように努めることが大切です。
「認知症の人の体力低下の速度は、認知症のない人と比べて速い」という特徴を言います。
高齢者を四つのグループに分け、それぞれのグループの年ごとの累積死亡率を5年間追跡調査した結果(長谷川和夫聖マリアンナ医大元名誉教授、日老医誌、7:630,1980)によれば、認知症高齢者グループの4年後の死亡率は83.2%で、正常高齢者グループの28.4%と較べると約2.5倍になっていました。他の2つのグループと比べても2倍近い開きになっていました。認知症グループホームなどの利用者の変化をみますと、はじめは元気で行動的であった人が、数年経過すると動きが悪くなって通所できなくなる例や、買い物、配膳などの共同生活ができていた人が室内に閉じこもるようになり寝たきりになる例などは決して少なくありません。
このようなことから、認知症の人は衰弱の進行が速いということが一般的に言えます。
しかし、個人により、発症年齢により、原因疾患により進行の速さが異なっているのも事実です。若年発症の認知症の人の中には、6~7年で寝たきりになる人もいれば、20年以上かけてゆっくり進行する人もいます。遺伝の影響の強い家族性アルツハイマー病の姉妹のケースでは、発症年齢はほぼ同じでしたが、家族の献身的な介護を受けた妹は5~6年長生きをしたという報告もありまから、介護などの社会的・家庭的要因によっても変化すると思われます。
認知症の症状自体、個人差があります。認知症かどうか疑われるほど症状が目立たない人もいれば、激しい症状を示す人もいます。糖尿病と診断されても、生活上の注意(食事や運動など)をするだけでよい人、数十単位のインスリン注射をしている人、合併症のない人、激しい合併症で苦しんでいる人など様々です。認知症も同じで、認知症とはこのようなものと決めつけないで、様々な症状を示している人がいることが普通であると知ることは重要です。
10. 介護に関する原則
「認知症の人が形成している世界を理解し、大切にする。その世界と現実とのギャップを、感じさせないようにする」。これが「介護に関する原則」です。
私は、認知症の人を介護する介護者に対して、
「本人の感情や言動をまず受け入れて、それに合うシナリオを考え演じられる名優になって下さい。それが本人にとっても、あなたにとっても一番よい方法です。そして、名優はときに悪役を演じなければなりませんよ」と話すことにしています。
認知症の人の世話をすることは、ときには大変つらく苦労が多いものです。介護者は家族のあいだで、あるいは経済的にも、また社会に対しても、いろいろな問題を背負いこむものです。そんな場合に自分自身も俳優であると発想することは、心の負担をほんの少しでも軽くすることにもなるはずです。
とにかく、認知症の人が、自分は周囲から認められているのだ、ここは安心して住めるところだ、と感じられるように日頃から対応することが、一番楽で上手な介護になるのです。