No.44–苦痛の訴え少ない終末期-在宅ケアには支えが必要
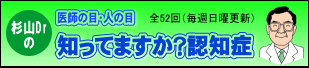 当会副代表理事の杉山孝博Drによる連載です。全52回、毎週日曜日と水曜日に新しい記事を追加します。
当会副代表理事の杉山孝博Drによる連載です。全52回、毎週日曜日と水曜日に新しい記事を追加します。
公益社団法人認知症の人と家族の会副代表理事・神奈川県支部代表
公益社団法人日本認知症グループホーム協会顧問
川崎幸クリニック院長
杉山 孝博
「おばあちゃんは、苦しまないで静かに逝くことができました。私がおむつを替えた後、振り返ったら呼吸が止まっていました」
看取ったばかりの姑の死を嘆くというより、むしろ無事穏やかに看取れたという満足感を感じさせられる表情で、介護者である嫁は、真夜中に死亡確認のため臨時往診をした私に対し感謝の言葉を述べた。
理解しがたい言動に振り回され、24時間見守りの必要な認知症の人の介護は、介護家族にとって大きな負担がかかる。しかし認知症の人の終末期は、苦痛の訴えが極めて少ないのが特徴だ、たとえがんがあってもモルヒネなどの麻薬を使う例はほとんどないと言ってよい。
大井玄・東京大学名誉教授が都立松沢病院外科病棟の進行がん患者についてカルテを調査した研究がある。それによると、認知症のない23名のうち、痛みを訴えたのは21人(91%)で、13人(57%)に麻薬を使った。麻薬を使った人はいなかった。
認知症は、終末期の苦痛や不安を、ベールをかぶせるように軽くする仕組みではないかと思いたくなる。
認知症の人は発病すると、さまざまな精神症状が多出する時期を経て、身体症状を合併する時期になり、最後に終末期に至る。
終末期に近づくにつれて医療的ケアが家族にとって深刻な問題となる。入院治療をするのか、在宅でどこまでみていけるかを考えなくてならなくなる。
在宅でみていく場合には、訪問診療や訪問看護による支えがあるかないかで在宅ケアの可否が決まるといえよう。主治医、訪問看護師、ケアマネジャー、ヘルパー、親族などが適時連絡を取り合うことが重要だ。
終末期では寝たきりとなり、食べ物も取れなくなって衰弱が進行する。呼吸器感染症にかかりやすくなり、せきが出たり、たんが絡みやすくなったりする。褥瘡もできやすくなる。突然の状態の変化が介護者にとって心配になるようになる。
在宅の認知症の人は、肺炎や心不全、腎不全といった合併症が原因で死を迎えることも少なくない。その場合には、それらの疾患の治療と終末期ケアが問題となる。
「認知症の人のケアはドラマである」と私は考えている。ドラマの幕引きにあたるターミナルケアに対する関心は非常に高い。
杉山孝博:
川崎幸(さいわい)クリニック院長。1947年愛知県生まれ。東京大学医学部付属病院で内科研修後、患者・家族とともにつくる地域医療に取り組もうと考えて、1975年川崎幸病院に内科医として勤務。以来、内科の診療と在宅医療に取り組んできた。1987年より川崎幸病院副院長に就任。1998年9月川崎幸病院の外来部門を独立させて川崎幸クリニックが設立され院長に就任し、現在に至る。現在、訪問対象の患者は、約140名。
1981年から、公益社団法人認知症の人と家族の会(旧呆け老人をかかえる家族の会)の活動に参加。全国本部の副代表理事、神奈川県支部代表。公益社団法人日本認知症グループホーム協会顧問。公益財団法人さわやか福祉財団(堀田力理事長)評議員。
著書は、「認知症・アルツハイマー病 早期発見と介護のポイント」(PHP研究所)、「介護職・家族のためのターミナルケア入門」(雲母書房)、「杉山孝博Drの『認知症の理解と援助』」(クリエイツかもがわ)、「家族が認知症になったら読む本」(二見書房)、杉山孝博編「認知症・アルツハーマー病 介護・ケアに役立つ実例集」(主婦の友社)、「21世紀の在宅ケア」(光芒社)、「痴呆性老人の地域ケア」(医学書院、編著)など多数。

